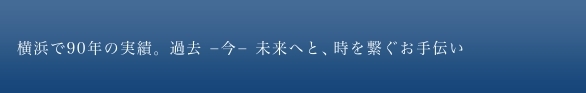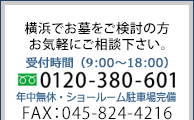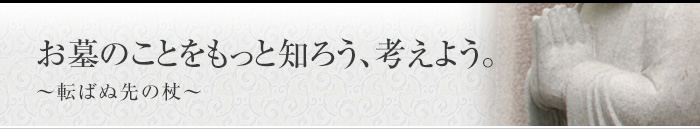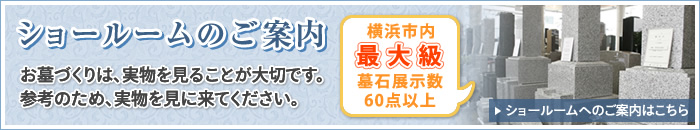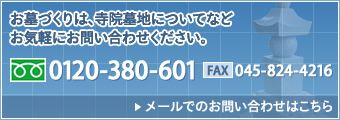- HOME
- [お墓のことを知る・考える] 専門家の対談
- 老後と死の諸問題:その2 成年後見制度
その2 成年後見制度
死の実感が私たちの生活から乖離していく中で、身寄りの有無にかかわらず、死を意識するようになったお年寄りの心の拠り所というものがあいまいになってきているように思われますが…。

介護のケースワーカーにきくと、老人からの相談で一番多いのは、「子供や次の世代に苦労をかけたくない」という話なのだそうです。
子供がいない人の相談もよく受けるそうですが、逆にまったく身寄りのない方というのは少数派で、問題なのは自分が死んだ後に遺骨を引き取り、供養してくれと頼めない程度の関係の身内しかいない、という人たちです。
身寄りのない老人でも、年金や貯金などなんらかのお金は持っています。
そのお金を、本人が亡くなった後、本人のために使うのが本当の供養だと思います。
では「本当の供養」とは一体何なのかを見つめなおす必要があると思います。

私は以前、成年後見制度※2について研究を行っておりました。
欧米ではこの制度は早くから発達し普及しているのですが、日本では比較的遅れていました。
どういう制度かと申しますと、たとえば身寄りのないお年寄りが例えば認知症などを発症したとき、介護施設で介護を受ける必要があるわけですが、身寄りがないとか、遠縁しかいないといった場合、誰もその人の財産の管理をする人がいないわけです。
財産がなくとも、たとえば生活保護や年金を受け、その中から病院などへの支払いを済ませるといった役割を誰かが果たさなくてはなりません。
こういう場合は、市区町村の区長などが後見人として申立てできるようにしようという制度なのです。
こうした人が亡くなれば死亡届を出し、埋葬許可を得て、埋葬をどうするか、墓はどうなるのか、誰が供養するのかといった問題が続きます。
身内の人がいる場合でも、人間、財産は相続したいけれども遺骨は相続したくないという人が多いのが実情です。
成田住職の先ほどからのお話を聞いていると、成年後見制度の後見人としては何も区長に限らず、本人の宗旨宗派に沿うのであれば、その地域のお寺の住職が位置づけられても決しておかしくないのではないでしょうか。